- 世界にまだない“おいしい”のために。
- ニチレイグループとは?
- 社員インタビュー
- プロジェクトストーリー
- ニチレイの働き方
- 採用情報
イノバジアン・クイジーン社
MEMBERこのプロジェクトに登場する社員
-
荒木 琢也
InnovAsian Cuisine Enterprises Inc
01 新たな成長のエネルギーを求めて、北米へ。
現在、InnovAsian Cuisine社(以降イノバジアン社)でChairman of the board(会長)を務めている荒木が、北米におけるニチレイフーズのビジネス拡大の役割を担うようになったのは、2000年代後半のこと。日本においては、少子高齢化という現実があり、先行き人口増が望める状態にはない。そこでニチレイフーズは、成長に向けての新たなエネルギーを求めて、北米市場での事業創造を模索していたのだった。
現地に降り立った荒木は、まず市場調査をはじめた。人口動態などの各種データを調べ上げ、街に足を運び、地域の人気飲食店のメニューや味を確かめた。
人口動態など各種データからは、アジア系をルーツとする人たちの人口の伸びが顕著であることが読み取れた。特に中国系の伸びが著しく、しかも若い世代が多く、先行き長い期間に渡ってのニーズを読むカギとなるように思えた。そしてアジアンフーズは現地でファーストフードのようにカジュアルに親しまれ、特に中華系は給食に供されることもあるくらいなのであった。
事業拠点をどのような形で置くか。こちらももろもろの検討の結果、イノバジアン社という、アジアンフーズの冷凍食品を企画・販売する現地企業の買収を決断。工場の新設といった他の選択より、効率よく早期から事業を始動できると判断できたからだ。
北米市場での、新事業のスタート。荒木の胸の内には、“絶対に成功させるのだ”という強い思いと情熱が沸き上がっていた。
02 様々な“常識”の違いを超えて。
買収が決まると、荒木は買収成立後の業務や組織統合に関する一連の実務をリードする役割を担った。統合によって生じる様々な障害を事前に想定し、あらかじめ対処を検討してから統合を進める手法(PMI)で実務を進めていった。
事前に課題点とその対処を検討し、統合の実務をリードしていた荒木たちであったが、文化や慣習の違いからくる、業務における“常識”の差の大きさには、戸惑わざるを得なかった。
ひとつは、時間の感覚。例えば、日々の報告書類の提出などは、しばしばおざなりにされた。決められたものを決められた期日までに提出する、という“常識”は、内容によっては大きなずれがあったのだ。業務の“納期”設定もしかり。日本企業のように、日単位で最短の工期を設定し効率よく動いてそれを達成しようとするのではなく、余裕のある週単位でのスケジュールを組むのが彼らの“常識”であった。
また、財布の感覚も、“常識”の違いのひとつだった。
日本でなら、ある一定以上の金額の物資の購入は、事前にしかるべき筋を通して許可を得て購入する。少なくとも、報告くらいはする。しかしイノバジアン社がオーナー企業であったからか、そのあたりは非常におおらかな運用がなされていた。
怒鳴りつける勢いで「こうしろ」と強制することもできた。しかし、荒木たちが目指すのはイノバジアン社を“現地の人が、現地の人に喜ばれるものをつくる”会社にすることであった。
そのため、荒木たちは可能な限り、現地の“常識”に合わせることを優先した。ただ、安心・安全・高品質な商品づくりのためであったり、上場企業のグループ会社として義務として行わなければならないという理由があることについては、一人ひとりの現地社員と向き合い、丁寧に理由を説明し、理解と協力を求めた。
説得のため、一人ひとりの現地社員と向き合った荒木。話合いの時間は、荒木と現地社員がお互いを知り合う機会ともなった。荒木は一人ひとりのキャラクターを知り、現地社員は荒木のキャラクターと共に、この事業に懸ける情熱を知った。そのうち相互に信頼関係が生まれ、事業の成功、そしていいものをつくりたいという荒木の想いはイノバジアン社スタッフ全員に共通の想いとなっていったのだった。
03 中華料理?いや、アメリカン・チャイニーズだ。
もうひとつ、プロジェクトが乗り越えなければいけない“常識”があった。
ここまで幾度か使ってきた言葉-アジアンフーズとは、大半が“中華料理”である。しかし、そう表現してしまうと、日本に住む私たちは、必ず誤解する。
麻婆豆腐、八宝菜、酢豚・・・日本住む私たちがイメージする“中華料理”とアメリカにおけるそれは、全く別のものである。もちろん、本場中国で供されるものとも、違う。
例えば、オレンジソースを使った酢豚風鶏のから揚げ。“照り焼き”チキン。極端なことを言えば、何かを春巻きの皮で巻けば、それはもう“中華料理”なのだ。アメリカン・チャイニーズともいうべき食文化、これこそがイノバジアン社が目指す味の方向性であった。
そのため、荒木たち日本人が「おいしい」と思う中華料理の味の“常識”では、現地の人々が「おいしい」と感じるアメリカン・チャイニーズの“常識”は判断できない。むしろ、荒木たちが高く評価した味は、現地ではうけない、と思っておいた方が良い。
そのため、商品開発に当たって荒木たちは、とにかく現地のアメリカ人が好む中華料理のメニューを研究。選定したメニュー候補を現地の委託先工場で試作し、イノバジアン社の現地社員が試食し判断を下す、というプロセスを踏んだ。
04 目指すは、アメリカのアジアンフーズNo.1ブランド。

かくして、イノバジアン社は次々とアメリカン・チャイニーズメニューの製品をリリース。売れ行きは順調で、2017年度の売上はおよそ143億円。統合前が43億程度だったことを考えると、的確に市場のニーズをとらえていることがわかる。また、その内訳は業務用が4割弱、家庭用が6割強であり、より一般消費者に受け入れられていることは注目に値する。
そのため、荒木たちは今後も消費者市場が求める商品の開発・販売を目指している。例えば、今後消費の中心となる、いわゆるミレニアル世代のニーズを意識した商品開発なども、選択肢の一つだ。
イノバジアン社としては、“現地のひとがつくる、現地の人に喜ばれるものをつくる”会社を、現地の人たちで運営していく、という統合以来のコンセプトを追求し続けていく。
そうして創られる“現地のブランド”が、やがては北米No.1のアジアンフーズブランドになることが、究極の目標だ。
伸びゆく北米市場。海外で活躍したい、と考える学生にとって、ニチレイフーズにおける北米事業は魅力的に映るかもしれない。しかし、荒木は『日本で仕事が出来ない人が海外に出て大活躍することはまずない』と考えている。
海外志望がある人こそ、勤めた日本企業でまず強み・弱みを深く理解し、その上で人に認められる仕事をすることをまずは目標とするべきで、それが海外で良い仕事をすることの近道と、荒木は考えている。言葉が話せるというのは、一つの能力であることは間違いないが、言葉よりも大切なのは、常識を乗り越えてでも事業を前に進めるような、ビジネスにおけるモチベーションの強さや、実力なのだ。
OTHER STORY 他のプロジェクトストーリー
ニチレイフーズ

ニチレイバイオサイエンス
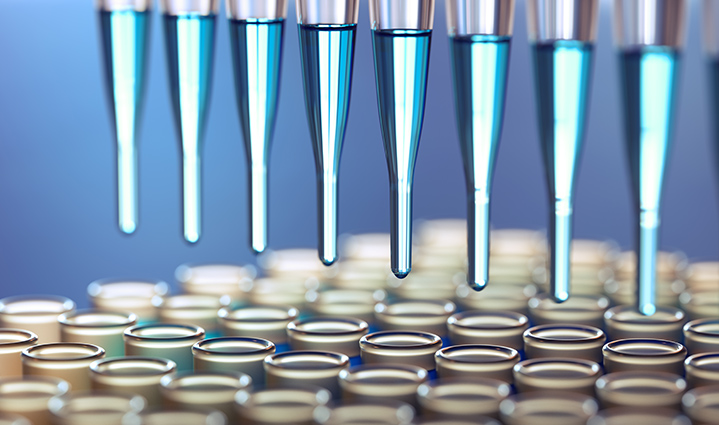
ニチレイフレッシュ

ニチレイロジグループ





