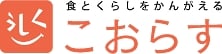氷の実験室 氷と温度変化
もともとニチレイは氷屋さんでした。
氷が大好きなニチレイはこの「氷の実験室」で、みなさんと一緒に「氷」の秘密をじっと見つめ考えていきたいと思います。
雪と氷が大好きなレイちゃんとロジロジくん、氷博士の石井先生と一緒に、氷の不思議に触れてみましょう。
やってみよう!
0℃の氷と100℃のお湯を混ぜると何℃になる?
0℃の氷と100℃のお湯を同量混ぜて、温度を測ってみましょう。
用意するもの
- 氷約1㎏
- 沸騰させた(100℃)お湯
- ザル
- 大きめのボウル
- 温度計

手順
- 1. まず、0℃の氷をつくりましょう。氷を冷蔵庫の中にしばらく置いておくと、氷の温度が上がり、0℃になったところでとけ出します。ときどきかき混ぜて全体の温度を均一にしながら半分くらいとかすと、0℃の水の中に0℃の氷が浮かんでいる状態になります。
- 2. お湯を沸騰させておきます(沸騰しているお湯は、ちょうど100℃です)。
- 3. 1の状態から、氷と水をザルで分けます。
- 4. 3の氷をボウルなどに入れて重さを量り、そこに同じ重さだけ沸騰したお湯を注ぎます。(やけどに注意!)
- 5. かき混ぜて氷をとかし、全部とけたところで温度を測ってみましょう
予想
お湯の温度は何℃になっているでしょうか?
-
A
50℃になる
-
B
50℃より高い温度になる
-
C
50℃より低い温度になる
- 答え
-
C 50℃より低い温度になる
0℃の水と100℃のお湯を同じ量混ぜると、約50℃になります(手順1でつくった0℃の水に100℃のお湯を同量注いで試してみましょう)。しかし、0℃の氷と100℃のお湯では、50℃よりもかなり低い温度(気温など条件にもよりますが、今回の実験では約15℃になりました。理論的には(熱の出入りがなければ)10℃)になります。
もっと知りたい!

教えて!氷博士
- 0℃の氷と100℃のお湯を混ぜて50℃にならないのはなぜ?
-
氷をとかすには、大きなエネルギーが必要です。
氷がとけて水になるためには、実はかなりのエネルギーが必要です。0℃の氷1gをとかして0℃の水にするのに必要なエネルギーは、約80cal(約334J)。水1gの温度を1℃上げるのに必要なエネルギーが1calなので、それと比べると、氷をとかすためには、かなり大きなエネルギーが必要(※)だということがわかりますね。 そのため、100℃のお湯に0℃の氷を入れると、お湯の持っている熱エネルギーの多くは、氷をとかすために使われてしまうので、100℃のお湯と0℃の水を混ぜた場合と比べて、温度が大幅に低くなるのです。つまり、「氷はとけるときに周りを冷やす働きがある」ともいえますね。
※この理由を説明するには、「物質の状態」がポイントになります。物質は、原子や分子など目に見えないたくさんの粒によってできています。また、物質の状態(気体か液体か固体か)は、物質をつくる粒の「動き回る度合い」によって決まります。固体は、物質をつくる粒の位置がほぼ固定されている状態なのに対し、液体は物質をつくる粒同士が互いに影響し合いながらも、動き回ることができる状態です。そして、粒が動き回るにはエネルギーが必要になります。つまり、氷(固体)が水(液体)になるときには、外からエネルギーを与えて、粒が動き回ることができる状態にする必要があるのです。
逆に、水(液体)が氷(固体)になるときには、余分のエネルギーが熱として放出されます。1gの水が氷になるときには、約80calのエネルギーが放出されます。過冷却状態(水が凍る瞬間を見てみよう 一気に凍る「過冷却」のひみつ(2)の「教えて!氷博士」 参照)の水が凍るときの温度変化を精密な温度計で測ってみると、-7~-8℃になっていた水が、凍っていくにしたがって温度が上がることがわかります。
この「氷の実験室」は、自由研究など幅広く活用していただきたいと思って作りました。
非営利目的での複製・転載などについてのご要望は、以下からお問い合わせ下さい。
2022年1月24日